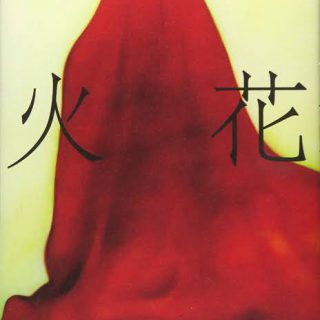吃音によって悩んでいる全ての人に読んで貰いたい小説です。
小説だから過大に表現している部分はあるのだけれど、友達や家族との『絆』を上手く描かれた作品になっています。
辛い時や悲しい時、周りかの『親切』が鬱陶しかったり、イライラしたりすることってありますよね?
僕も吃音で落ち込んでいる時の、友達や先生からのフォローって、本当に嫌で堪らず『放っといてほしい』というのが本音でした。
でも周りからのフォローは冷静に考えると有難いし、吃音を笑わないで付き合ってくれた友達は、30歳を過ぎた今でも良き友として付き合いが続いています。
“周りが色眼鏡を付けて自分を見ている“と思いがちなのだけれど、“自分が色眼鏡を付けて周りを見ている“という事実に気がつかなければ、大切な友達や家族を失ってしまい、本当に一人ぼっちになってしまいます。
小説『僕は上手にしゃべれない』の主人公である柏木を通じて、本当に大切なものは何かを見極めて下さい。
周りは自分を色眼鏡を付けて見ている
大人になった今では、もう自分の吃音について“世の中で1番辛い“こととは思うことはありません。
辛いこと、苦労している人は世の中にいっぱいいますし、上を見上げればきりがありません。
でも『吃音なんて』とは割り切れないということは今でも変わりませんけどね。
世の中に『辛いことランキング』みたいなものがあったとすれば、吃音はかなり上位に食い込むのではないかと思っています。
それでも幼い頃や学生の頃、思春期の頃はそんな冷静には居られず『上手くしゃべれない自分は、世の中で1番辛い』と思ってしまいます。
- 笑われる、真似される、バカにされる
- 白い目で見られる
- 怖がられる
そんな周りからの反応に悔しさや悲しさ、怒りや恐怖といった色々な感情を抱き、悪い場面ばかり思い出となってしまいます。
いつからか、周りは自分の事を“変な話し方をする人“という色眼鏡を付けてみていると勘違いしてしまうのです。
友達や家族でさえ理解出来ない苦しみ
吃音の発症は100人に1人です。
学校の中に1人や2人はいる程度の数値であり、ちょうど、知的障害者がいる程度の人数なのではないでしょか?
僕の小学校では”バカ”や”アホ”の代わりとして”キチガイ”という言葉がよく使われていました。
また「知的障害のマネ」といった遊びが流行ったりしました。
それを聞くたび、見るたびにズキズキと胸が痛むのは、僕が同じ様に吃音を真似された経験があるからなんでしょう。
だけどそんな吃音がある僕らでさえ、知的障害のある方の気持ちは分かりません。
また心の何処かで『かわいそう』などと思ってしまっている自分もいるのです。
同じ様な経験をしてきている僕らでさえ、色眼鏡をかけてしまっているけれど、それは赤や黄色や黒色の“イタズラな色眼鏡“ではなく、“クリアで純粋な色眼鏡“なのではないでしょうか?
友達でも家族でも、流暢に話せる人からすれば、吃音は理解し難く、眼鏡を付けないと見ることはできません。
それでも、それは「何とかしたい」という目を凝らすための眼鏡に他なりません。
確立した医療法がないことや、昔の誤った認識から、そんな方のアドバイスは
- 落ち着いて話しなさい
- ゆっくり話しなさい
- 焦らないで話しない
など、ありふれた当たり前の言葉ばかり。
そんな的外れな言葉を幾たびにも聞かされると、他の誰でもない、自分自身が色眼鏡をかけて世間を見て、友達をみて、家族をみる様になってしまいます。
自分が色眼鏡を付けていたと気がつくこと
小説『僕は上手にしゃべれない』の主人公『柏木』は、やっぱりイタズラな色眼鏡をつけた人達によって、いっぱい傷付きます。
それを輪にかけるように、姉からの思いやりの眼鏡にもイライラします。
怒りは爆発し、友達も姉も突き放すことになるのですが、とある人からの一言によって、本当に大事なコトに気がつくのです。
小説なら、漫画なら、映画なら、ベストなタイミングで『とある人の一言』が登場するのですが、現実世界ではそうはいきません。
だから、この小説を通じて感じて欲しいのです。
当時の僕には『とある人の一言』はありませんでした。
時間が経って、30過ぎのおっさんになってから分かる境地です。
それを10代・20代のうちに分かって、大事にすることができれば、きっとあなたの人生は豊かなモノになっていくでしょう。
また思いやりの言葉に気がつくことができると思います。
恐るものなんてない
吃音によって諦めた夢とかありませんか?
僕にはあります。
大きな夢を諦めたことが。
吃音があるとどうしてもブレーキがかかる場面があり、僕は高校時代に、吃音だからといって野球部のキャプテンの座を譲りました。
僕の高校では甲子園常連校で、僕の代にも甲子園出場を果たしています。
つまりキャプテンを勤めれば、甲子園に、少なくともベンチには入れたのです。
しかし人前での話すことや、号令をすることに怯え、キャプテンは辞退しました。
夢の甲子園で、僕はベンチにも入れず、スタンドでただ大きな声を出して終わりました。
本当は怖がることないんです。
やってみればいいんです。
それをこの小説では教えてくれます。
どもって、どもって、どもり倒しても、本気の言葉を発声すれば、気持ちは伝わります。
それでも出来ないことは、やって貰えばいいんです。
僕が評価されたのは、号令をかけることではないし、人前で話すことではないのです。
チームを引っ張るということです。
少なくとも、当時の僕がこの小説を読んでいれば、もっと長い時間悩んだことでしょう。
簡単に辞退なんてしなかったでしょう。
こんなにも後悔しなかったと思います。
吃音だからって怖がることはありません。
あなたには何でもできる。
そんなことを最終章で教えてくれます。
是非とも、一度下さい。